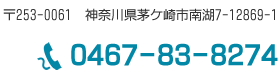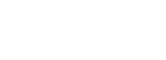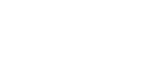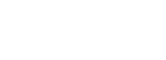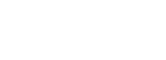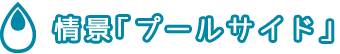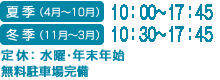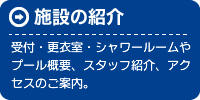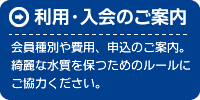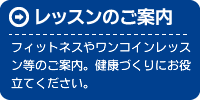2025/07/03
ひよどり
プール玄関前に鵯(ひよどり)の群が大集合、なにか美味しいものがあったのでしょうかしきりに啄んでいました。鵯は群れを作って行動します。椋鳥(むくどり)もそうですね。芝刈りをすると直に集まってきてなにか啄み始めます。草丈が短くなって餌が探しやすいのですね。芝刈りは草下の虫たちにとっては大変な災害なのかもしれません。この日は少し風が吹いていましたから、何かの種が飛ばされてきていたのかもしれません。鵯はかつては渡り鳥だったようですが今や留鳥、雑食性で草の種子や木の実、昆虫も食するそうです。甘いものが好きで蜜は大好物だとか。豊かな緑が多様な生物を育みます。大事にしていこうと思います。


(7/3以下、柴橋さん投稿です。)

ヤブカンゾウ(藪萱草)の花のこの色を何色と形容しようかと思案中、「萱草色(かんぞういろ)」という表現があることを思い出しました。この花に由来する色なのです。萱草の別名はワスレグサ(忘れ草)。物忘れが酷くなる、という訳ではなく…… 別離の悲しみをも忘れさせる色という意味なのだとか。そのためか、平安時代には何と喪服の色として使われていたのだとか。

先々週にもご紹介したヒメヒオウギズイセン(姫檜扇水仙)です。こうして全体を眺めてみると、花柄は短く、花が主軸に密着しながら交互に出ていることがお分かりかと思います。穂状花序(すいじょうかじょ)と呼ばれる型です。花は下向きに咲いているので香りを試すには姿勢が些か窮屈なのですが、刺激的な、でも魅力ある香りが楽しめます。

先週ご紹介したナンキンハゼ(南京櫨)は、下部に雌花を付けた花序も伸び始めました。雌雄混合のこの花序の場合は、雌花の方が雄花より先に咲きました。写真は開花した雌花。と言っても、三裂した花柱だけで飾り気は一切ありません。早くも子房が膨らみ始めています。雄花も雌花も飾り気は全くないのに、南京櫨の花は意外にも仄かに良い香りがします。香りをお試しなさるならば、アブラムシやアリには気を付けられますように。

芝生に混じってヒメヤブラン(姫藪蘭)の淡紫色の花が咲き始めました。面白いことに、雄蕊は花の中心から偏り、雌蕊はその雄蕊を避けるかの様に伸びます。

旧第一病舎南東のモッコク(木斛)が小さな蕾を付け始めました。横に張り出してから下向きに。姿は地味なれど甘い香りのする花が開くのが楽しみです。

プール棟の東側の壁に咲くコエビソウ(小海老草)の花です。朱色の苞(ほう:花の基部にある特殊化した葉のことを言います。よく知られた例では、ブーゲンビリアの花に見える部分が、じつは苞そのものです。)が重なって、確かにエビの様に見えます。白く突き出たエビの尾の部分が花本体で、上下に開いた花弁から雄蕊と雌蕊が覗いています。

マサキ(柾)に沢山の小さな花が満開です。中央部に発達した花盤、その中央から立ち上がる雌蕊、花盤の縁からピンと伸び出る4本の雄蕊、それを境とする4枚の花弁、機能的な構造の花です。花蜜が多く、この写真ではアリが。マサキの花は蜂蜜の蜜源の一つとなっているそうです。

先々週ご紹介したサンゴジュ(珊瑚樹)は花が終わり、幼果の姿となりました。花柄は果柄となり、いつの間にやら赤味を帯びてきました。珊瑚に変身中といったところでしょうか。

タブノキ(椨の木)の花柄も果柄となってすっかり赤く染まりました。その先には美しい緑色の球体となった果実が。対称性を保った花からの果実だけのことはあります。軈てはこれまた美しい黒紫色の球へと変化していきます。

ブラックベリーも輝きのある赤い果実の姿となりました。和名の一つ、セイヨウヤブイチゴ(西洋薮苺)の名に合った姿です。熟すと、もう一つの和名であるクロミキイチゴ(黒実木苺)に相応しく黒い実となります。
Copyright (C) 2019 太陽の郷プールガーデン. All Rights Reserved.