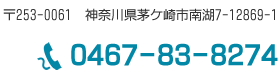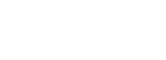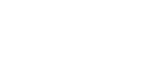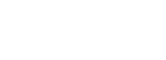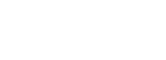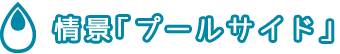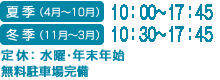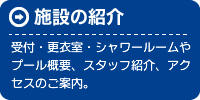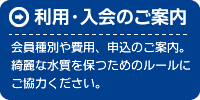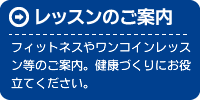2025/07/09
水鉄砲
7月3日、西浜小学校の2年生100名が夏の庭園観察にやって来ました。七夕間近で竹を持ち帰りました。1年生やなかよし学級の子らも来たのでいつにも増して賑やか、庭園は元気に溢れました。
織姫彦星の話に交えて竹で水鉄砲が作れる話になり、水鉄砲用の竹の欲しい子は学校から帰ってからもらいに来たら伐ってあげますという約束をしました。午後、幾人かやって来ました。水鉄砲は一節分の竹の片方を節の外側でもう一方を節の内側で切り、節の円の中央部にキリで小さな穴をあけます。竹筒の太さに合せて先端に布を巻きつけた棒を作り、水を入れて節のない側から押せば、ぴゅーっと飛び出ます。みんなでよく飛ばしっこをやったものです。半世紀の時空を超えてはるか昔が鮮やかに蘇るのでした。素朴な遊びが昔の少年と今の子らを友達にしてくれました。



(7/10以下、柴橋さん投稿です。)

連日猛暑が続きます。方向を変えながらパルス状に散水しているので、こんなパターンとなって見えます。謂わば大きな速射水鉄砲。太陽を背にして見れば、虹模様も。

華やかで香りも素晴らしいヤマユリ(山百合)が咲きました。花の重みで、倒れる様に下を向いています。かつては横浜港から輸出もされていたのだとか。神奈川県の県花となっているのも、そういう歴史があるからなのでしょう。

こちらはオニユリ(鬼百合)。三倍体であるために種子は作らず、葉腋にムカゴ(零余子)を大量に作って撒き散らすことで増殖します。強くはないのですが、良い香りです。ただし、開花してからの時期、天候、温度や湿度によるのか、香りを楽しめるのは限られた時期の様です。なので、正確には、良い香りがするときもあります、です。

先週ご紹介したモッコク(木斛)は、あっという間に開花したらしく、観に行った日には、もうこんな状態でした。花の命は短くて… 独特の香りはまだ残っていました。

ネズミモチ(鼠黐)にカナブン(金蚉)が獅噛みついています… 蟻が集っているので、最期を迎えたのか… 足掻く様にモソモソと… いえいえ、ネズミモチの花の蜜が大好物のハナムグリ、正確にはシロテンハナムグリ(白点花潜)が、蟻達と共に、食事を楽しんでいる最中なのでした。受粉を助ける益虫です。色々と食害を起こすコガネムシ(黄金虫)とは一緒にしないで下さい。

ここにも蟻が多数群がっています。マテバシイ(馬刀葉椎)の果実です。果実ですから蜜を出すことはないのに何故… 不思議に思ったのですが、アブラムシが分泌した甘露に蟻が集っているのではないか、と推察してみました。でもアブラムシの姿はなく… 確証は得られませんでした。

マテバシイの果実は、1年半かけて成熟します。前の写真は一年前に結実した果実です。これが熟して秋にドングリ(団栗)になります。で、これが今年の花が結実した姿。まだ、何やら枝にできた腫物の様な姿です。

こちらは歴とした植物の蜜に引き寄せられた蟻達です。と言っても、蜜は花ではなく葉の基部にある花外蜜腺から出ているので、不思議な光景ですが、花もまだ咲いていないのに蟻が集まっています。アカメガシワ(赤芽柏)の葉です。

全く珍妙な作りですが、これがセンリョウ(千両)の花(正確にはこの個体はキミノセンリョウ(黄身千両))です。黄緑色の球体が雌蕊。その上部に栓の様なものが見えますが、それが柱頭です。そして雌蕊に付随した白っぽい球体が雄蕊。その一部に縁が黒っぽい孔が花粉を放出した葯です。この姿ですから、とても虫媒花とは思えませんが、例は少ないものの訪花する甲虫類が観察されているそうです。はて、風媒花なのか、虫媒花なのか。

千両と来ればマンリョウ(万両)ですが、こちらは真っ当な花です。今は未だ蕾状態。千両より重みがあるということで、下向きに咲きます。花柄、額、花弁、全てが蕎麦滓だらけなのですが、果実になるとそんな時期があったなどとは思えない美しい赤になります。
Copyright (C) 2019 太陽の郷プールガーデン. All Rights Reserved.