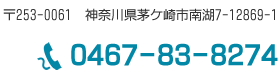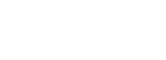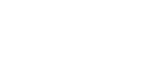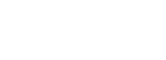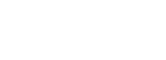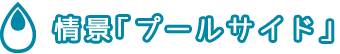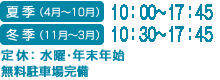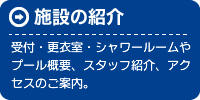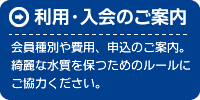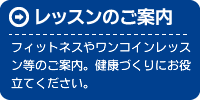2025/10/08
ツユクサ
芝生の中ほどにツユクサの一群を見つけました。ツユクサと言えば、春3~5月頃に芽生え、夏の6~9月頃に花咲くものと思い込んでいましたので、この時期は最後の群落でしょうか、青色が鮮やかです。早朝に咲き昼にはしぼむんだそうです。次から次へと日々違う花を咲かせ続けてくれるのですね。この後、実を結んで種子が出来、来年の発芽へと繋いでいくのですね。彼岸花も終わり、花数の少なくなった庭園を飾ってくれています。


(以下、柴橋さん投稿です)

赤の彼岸花にやや遅れてシロバナマンジュシャゲ(白花曼珠沙華)が咲いています。赤の色違いには違いありませんが、赤の彼岸花が不稔性なのに対して、白花曼珠沙華の方は結実します。そんな白花曼珠沙華は、このショウキズイセン(鍾馗水仙)と赤の彼岸花の交配種なのだとか。園芸品として扱われている鍾馗水仙の方が紅白の彼岸花からの交配種かと思っていました。

斑入りの葉ですから野生種ではなく園芸品種なのでしょう。ヤブラン(藪蘭)が淡い紫色の小さな花を総状に多数つけています。雌蕊が雄蕊を避けるかの様に位置しているのは、姫藪蘭とも共通しています。

早いものはもう実になって熟すのを待っている状態ですが、この個体の様にまだ花の状態のものも見られます。ノブドウ(野葡萄)です。蜜が豊富で虫達には大人気なのですが、饗宴も終わって蜜源ももうすっかり空になってしまった様です。

赤褐色の小穂から無造作に半透明の髭が伸び出ているといった感のハマスゲ(浜菅)です。髭の正体は三裂した花柱なのでありました。

セイタカアワダチソウ(背高泡立草)です。どこにでも無闇に生え出てくる、すぐに巨大になる、繁殖力が強い、花粉を飛び散らす、などなどの理由からか兎角嫌われがちです。でも花粉症を引き起こす犯人とされたのは誤解に基づいた冤罪。どこにでも生え出るという点は、紛れ込んだ外来種が日本の気候や土壌に合い過ぎてつい羽目を外してしまったといったところでしょうか。

どこにでも無秩序に生え出て繁殖力が強いという点はヨモギ(蓬)も同じ。こちらは花粉症を本当に引き起こすという点ではよりタチが悪いのに、春先の若葉が草餅(蓬餅)でお馴染みのせいか、あまり悪く言われることはない様です。夏を過ぎて成長した姿には、春先のあの面影は今何処。咲き方が雑然としている様に見えるかもしれませんが、中心部に両性花、それらを囲む様に雌花という具合に、きちんと配されています。

花からは、どうして栴檀と冠されているのか分かりません。ましてや、ひっつき虫とも称される実からは、とてもとても。センダングサ(栴檀草)、花から明らかな様に菊の仲間です。栴檀と葉の付き方や形が似ているから、この名なのだとか。

キクの仲間を3種紹介しましたが、キク科の花は、小さな花(小花)が沢山集まってそれが一つの花の様に見える点が特徴です。そういった小花の集まり具合が上記3種ではやや雑然としていますが、そこが整然としているのがコスモス。何しろコスモスの名前の意味するところは宇宙の秩序だそうですから、然もありなんでしょうか。

まだ雌蕊の痕跡を僅かに残しているとはいえ、開花して10日を経て、アキニレ(秋楡)は早くも若い果実となりました。形状は平べったい薄焼き煎餅ですが、色はまだ初々しい萌黄色。焼き上がりにはもう少し時間を要します。

最後はおめでたく赤と白のツートンカラーの小花。慶事の際に使われる紅白の水引に因んで、その名もずばりミズヒキ(水引)です。朝に開き、夕方には閉じてしまうお行儀の良い花です。花が小さい上に、細長い花茎は僅かな風にも揺れるので、撮影にはタイミングを待つ根気が必要です。
Copyright (C) 2019 太陽の郷プールガーデン. All Rights Reserved.