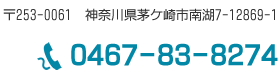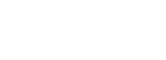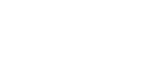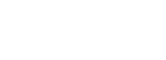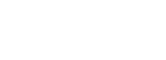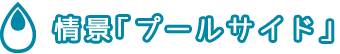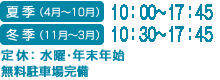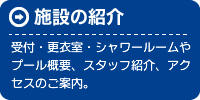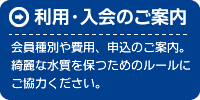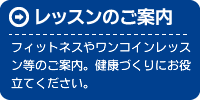2025/05/07
楠
楠が庭園のそこかしこで萌黄色に輝いています。ここには太陽の郷玄関前ロータリーの大楠、第一病舎北の大楠を横綱格として芝生の中央部や正門近くに楠が点在し、一斉に開花時を迎えて萌えいずるが如くです。第一病舎北の大楠は、青空の下、楠らしい広がりの樹形も見事に病舎北側の屋根を覆わんばかりの勢いです。建物をこするようになると楠には、この先、枝払い等の手が入れられることになります。芝生の楠も富士見台からの富士山を遮るようになると刃が入れられます。自然との調和を念頭に庭師の樹木との語らいが続いていきます。


(5/8 以下、柴橋さん投稿です)

東の生垣、フジ(藤)に代わって、甘い香りを漂わせているのはスイカズラ(吸葛)。常に二つペアで咲いています。初期は上縁を仄かに薄紫に染めた純白、徐々に薄黄色へと変わっていきます。常緑ですが冬には葉を丸めて寒さに耐えている様な姿になることから、「忍冬」とも書かれたり、呼ばれたりもするのですが、1年を通して観ていると、どうもそういう姿を見せるのは冬に限ったことではない様です。

そのスイカズラの香りをも、咲き始めるや、一気に圧倒する様になったのがテイカカズラ(定家葛)。個々の花の強い芳香に加え、南北に長い生垣一面に広がっているのですから、それも当然です。名前の「定家」とは、かの藤原定家(800年も前!)のことで、後白河天皇の第三皇女であった式子内親王を想い続けた定家が、死後も彼女を忘れられずに遂に葛となって彼女の墓に絡みついたという、金春禅竹(こんぱるぜんちく)作の能に基付いています。う〜ん、凄まじきかな、この情念。

丸池に近付くと、これまた別の甘い香りが。アキグミ(秋茱萸)の花です。葉が丸っぽいので、マルバアキグミ(丸葉秋茱萸)でしょうか。咲き始めは白く、軈て徐々に薄黄色へと変わっていきます。花弁はなく、筒状の萼の先が四つに分裂しているのが恰も花弁の様に見えている、ということの様です。

丸池から見て旧院長室棟を前景にして、高木のハリエンジュ(針槐)が青空を背景に白い花を満開に咲かせています。真下に近づくと、時折ですが下降流のおかげか、甘い香りが漂ってきます。別名のニセアカシアの方が馴染みがあるかも知れません。甘い香りからも想像は難くないと想いますが、蜜源として有用で、「アカシアの蜂蜜」というのは、ニセアカシアから集められた蜂蜜のことです。「ニセ」とは付くものの本家よりも有名ですし、慣用として定着しているので、不正表示とか野暮なことは言わないでおきましょう。

ひょうたん池付近は、辺り一面この甘い香りがいっぱいです。誰もがナツミカン(夏蜜柑)の名で呼びますが、じつは商品名として付けられた名前だそうで、元々はナツダイダイ(夏橙)と呼ばれていたのだそうです。蜂蜜が採取されるのみならず、香水にも利用されるほどの香りです。

今の季節、芝生の真ん中に育つ大木のクスノキを始め、庭の彼方此方のクスノキ(楠)が遠目に全体的に白っぽく見えます。小さな花が咲いているからです。雄蕊と雌蕊の間の黄色の腺体が目立ち、蜜もいっぱい。クスノキは「樟」とも表されますので、その字通りの樟脳か、英語名に由来するカンフル剤の匂いを想像される方も多いのではと思いますが、爽やかな甘さの香りの花です。蜂蜜の蜜源にもなっている様ですが、あまり知られていないのではと思います。

クスノキを背景とする、正門正面の低木、ニシキギ(錦木)は錦の織物の様な秋の紅葉が見事なのですが、今の時期は地味ながら小さな花を枝一面に咲かせています。花盤は蜜でいっぱい、そのせいで輝いて見えます。短い口を持つある種の昆虫にとっては好都合なのでしょう。花には香りはありませんが、採取される蜂蜜には特有の香りと風味があるのだとか。

ニシキギの周囲を始め、庭の彼方此方に現れたコバンソウ(小判草)。今やどこにでも見られますが、小判に似た穂が風に揺れる姿を愛でるために、明治時代に観賞用として態々ヨーロッパから導入されたのだとか。確かに艶やかな光沢のある萌黄色の穂が細い糸の様な枝に垂れて揺れる姿は美しくはありますが、はて、鉢植えにでもして鑑賞していたのでしょうか…

美しい実を沢山つけるので秋には生花やリースによく使われるツルウメモドキ(蔓梅擬)ですが、この時期には地味な花を沢山咲かせています。雌雄異株で、これは雄花。名前とは違い梅の花には全く似ていませんが、抑この名前、梅の花に似た花を咲かせる「ウメモドキ」なる低木があって、そのウメモドキに似た果実を稔らせる蔓性の植物ということに由来するそうですから、あくまで蔓性の「ウメモドキ」擬き。元祖の梅には花が似ていないのもまぁ無理はないか… 植物分類上はニシキギの仲間です。

ツルウメモドキが生えている芝では、オオイヌノフグリよりも寧ろタチイヌノフグリの方が目立つ様になりました。オオイヌノフグリの花の盛期を過ぎる頃から咲き始めましたし、這う様に伸びて花を付けた先の部分だけが立ち上がるオオイヌノフグリに対し、タチイヌノフグリは全体が真っ直ぐに立ち上がっているので目立つのです。ただし、花はオオイヌノフグリよりもずっと小さいのでお見逃しなき様。
<<「金雀枝」前の記事へ
次の記事へ「西浜小学校2年生春の庭園観察」>>
Copyright (C) 2019 太陽の郷プールガーデン. All Rights Reserved.